前の10件 | -
日本共産党はどこへ行く? [社会情勢]
本年1月、日本共産党が党大会を開いた。
そこで共産党にしては極めて珍しい、とはいえ極めて穏当な批判「的」な意見が出された。
昨年2月に除名され大きな話題となった松竹氏の除名について、その処分の速さと重さについてだ。しかもそれは彼女が共産党の活動をし、人民と対話をすすめる中で感じた結論でもあった。
これに代議員3名がかみついた。多くの代議員が発言を求めて大会運営に通告を行っているとのこと。なのに反対意見が3人も。しかも地区委員長(*)に加えてトリは赤旗の政治部長までお出ましだ。
ま、組織された反論なんでしょうね。これって。
*新宿地区委員長の中野顕氏は松竹氏のせいで「新宿では2千~3千票減ったという実感」と発言したが、あれれ?党の公式発表では松竹氏除名の影響はなかったんじゃないの?
実は大山氏は松竹氏を除名をするなと言っているのではない。拙速な判断をせず松竹氏から出されている除名処分再審査請求を適切に行えとの意見だ。これは手続き論であって批判ですらない。
しかも大会最後の「結語」で新しく委員長になる(「結語」の時点では副委員長)の田村智子氏が、この大山県議団長の発言をことさらにとらえて過剰な非難をしたものだから、これが各所で「パワハラ」と指摘されて大騒ぎ。
日本共産党大会結語での田村智子氏発言はパワハラではないのか?
*討論のまとめを共産党は「結語」と表現する。これは党大会など共産党中央が関わる会議で使われる「共産党語」でもある
この一連の顛末はマスコミでも報道された。とはいえ共産党のニュースバリューはここ数年で極めて低下したため、それほど衆目を集めてはいないが。
大山氏は大会後、ショックで精神状態が悪くなっていたようだ。また最近明らかになったところでは、党大会以前からTwitterやFacebookなどをチェックされていて、党中央から指導されていたらしい。
彼女の党大会での発言と過剰な-おそらくは-組織された批判は、そして「結語」でのパワハラ発言は、準備されたものだったということだ。
大山奈々子 日本共産党神奈川県議団長のTwitter(*)
*私は「X」とは表現しません
何と驚くべき組織になったのだろう。かつてはこうしたことは隠されていたと思うのだが、こうして表に出てしまうことに何の抵抗もなくなっている。そこがこの党の劣化を象徴しているように私は思うのだ。
さて「何の抵抗もなくなっている」と私は評した。
その証明がこの間共産党の「しんぶん赤旗」で公然と出されている論評だ。そして新たに書記局長となった小池晃氏の記者会見の内容だ。そこでは結語をパワハラと指摘する人に、あれは反論であってパワハラではないと居直る姿勢だ。
そしてその尻馬に乗って、共産党関係や支持者(*)がTwitterやFacebookでもっとあからさまな目を覆いたくなる意見をまきちらす。
*共産党員ではないと公言して支持者を名乗る、共産党中央の意見を垂れ流すTwitterアカウントってめちゃくちゃ多いんすよマジで。そんなレアキャラ現実世界のどこにいるっての
これに違和感を持たない人がいようか。案の定多くの人が批判している。それもネトウヨ系ではなく、これまで明らかに共産党を支持し期待してきた人たちが、だ。
そりゃそうだ。ジェンダー平等、ハラスメント撲滅とかで共産党に接近した人は、最近特に多いだろう。それらの人々から見たら、現在の共産党内は古くてカビの生えた旧態依然とした組織だった。
期待した分、失望はより大きい。これらの人々を裏切ったツケは早晩共産党に降りかかる。そして共産党はこのまま崩壊してしまうのだろうか。
いや。
そこで共産党にしては極めて珍しい、とはいえ極めて穏当な批判「的」な意見が出された。
昨年2月に除名され大きな話題となった松竹氏の除名について、その処分の速さと重さについてだ。しかもそれは彼女が共産党の活動をし、人民と対話をすすめる中で感じた結論でもあった。
これに代議員3名がかみついた。多くの代議員が発言を求めて大会運営に通告を行っているとのこと。なのに反対意見が3人も。しかも地区委員長(*)に加えてトリは赤旗の政治部長までお出ましだ。
ま、組織された反論なんでしょうね。これって。
*新宿地区委員長の中野顕氏は松竹氏のせいで「新宿では2千~3千票減ったという実感」と発言したが、あれれ?党の公式発表では松竹氏除名の影響はなかったんじゃないの?
実は大山氏は松竹氏を除名をするなと言っているのではない。拙速な判断をせず松竹氏から出されている除名処分再審査請求を適切に行えとの意見だ。これは手続き論であって批判ですらない。
しかも大会最後の「結語」で新しく委員長になる(「結語」の時点では副委員長)の田村智子氏が、この大山県議団長の発言をことさらにとらえて過剰な非難をしたものだから、これが各所で「パワハラ」と指摘されて大騒ぎ。
日本共産党大会結語での田村智子氏発言はパワハラではないのか?
*討論のまとめを共産党は「結語」と表現する。これは党大会など共産党中央が関わる会議で使われる「共産党語」でもある
この一連の顛末はマスコミでも報道された。とはいえ共産党のニュースバリューはここ数年で極めて低下したため、それほど衆目を集めてはいないが。
大山氏は大会後、ショックで精神状態が悪くなっていたようだ。また最近明らかになったところでは、党大会以前からTwitterやFacebookなどをチェックされていて、党中央から指導されていたらしい。
彼女の党大会での発言と過剰な-おそらくは-組織された批判は、そして「結語」でのパワハラ発言は、準備されたものだったということだ。
大山奈々子 日本共産党神奈川県議団長のTwitter(*)
*私は「X」とは表現しません
何と驚くべき組織になったのだろう。かつてはこうしたことは隠されていたと思うのだが、こうして表に出てしまうことに何の抵抗もなくなっている。そこがこの党の劣化を象徴しているように私は思うのだ。
さて「何の抵抗もなくなっている」と私は評した。
その証明がこの間共産党の「しんぶん赤旗」で公然と出されている論評だ。そして新たに書記局長となった小池晃氏の記者会見の内容だ。そこでは結語をパワハラと指摘する人に、あれは反論であってパワハラではないと居直る姿勢だ。
そしてその尻馬に乗って、共産党関係や支持者(*)がTwitterやFacebookでもっとあからさまな目を覆いたくなる意見をまきちらす。
*共産党員ではないと公言して支持者を名乗る、共産党中央の意見を垂れ流すTwitterアカウントってめちゃくちゃ多いんすよマジで。そんなレアキャラ現実世界のどこにいるっての
これに違和感を持たない人がいようか。案の定多くの人が批判している。それもネトウヨ系ではなく、これまで明らかに共産党を支持し期待してきた人たちが、だ。
そりゃそうだ。ジェンダー平等、ハラスメント撲滅とかで共産党に接近した人は、最近特に多いだろう。それらの人々から見たら、現在の共産党内は古くてカビの生えた旧態依然とした組織だった。
期待した分、失望はより大きい。これらの人々を裏切ったツケは早晩共産党に降りかかる。そして共産党はこのまま崩壊してしまうのだろうか。
いや。
日本社会の劣化が印象付けられた2023年 ~このまま崩壊するのか、それとも [雑想]
日本共産党の赤旗スクープから始まった自民党、特に安部派の金権腐敗が留まることを知らない勢いである。
以下赤旗主張から
主張 松野氏の裏金疑惑 「答え控える」はもう通用せぬ
主張 自民党派閥の裏金 疑惑底なし 政権担う資格ない
ついでに東スポも
田崎史郎氏 安倍派〝疑惑の方程式〟スクープの赤旗に「また赤旗に抜かれてしまった…」
*テレビ番組のまとめみたいな「記事」だが...。なお田「﨑」が正しい
今年の年末は、自民党「安倍派」崩壊の序曲で幕を閉じる。この事件は本当に救いようのない疑獄事件で、「パーティー券」が事実上企業献金の抜け道として使われたのみならず、それが政治資金規正法逃れとして自民党の安部グループが長年利用してきたということである。
言うまでもなく安倍グループは、2012年から長らく政権首班として日本を極めて悪い意味で支配していた人々である。マスコミを支配し、官僚を恫喝し、日本の民主制度を根底から破壊してしまった連中である。
そして森友加計学園問題で公文書の書き換えを行わせ、桜を見る会では政権による私物化を推進、子飼いのジャーナリストによる性犯罪をもみ消すことまでやってのけた政権である。
カルト宗教「統一協会」に野党時代に特に接近し、その支配と拡大を放置どころか一緒になって進めてきたともいえる勢力が自民党、特に安部派である。
「こんな人たち」が日本の政界の中枢にいて日本政治のかじ取りを進めていた。その結果が、日本の経済と世界における位置が徹底的に沈滞したことだ。
その政権をネットでは擁護する意見が大きかったが、それすらも政権が運営していた-Dappi問題でその一端が見えたが-ことすら明らかになった。
そして私を何より絶望的な気分にさせるのは、これらの問題が、2022年夏に安倍晋三が暗殺されてから噴き出した問題ということだ。もちろんモリカケサクラ問題の頃も我々は問題視していたが、マスコミも世論も動きはそれほど大きくはならなかった。
たった一人の人間が殺されたことで、ここまで様々な問題が顕在化して社会問題となっている。いやいや、生きているうちに顕在化しないのは何故なんだ。いったいどうなっているんだ。何なんだこの日本社会は。何かが崩れてしまった。
これは日本の社会状況が極めて非民主的な空気の中で動いていることに他ならないのではないか、私はそう思うのだ。そしてそれらを安倍政権とそれ以降の政権が作り上げてしまった。
安倍政権の犯罪はまさにそのような社会を生んでしまったことにあるようにも思う。
一方...
私はこの間「日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと」として連続で記事を書いた。
*記事表題はアルチュセールのパロディですが
今年の1月から始まった「除名問題」の対応を1年近く見続けてきた。そして-今回自民党金権腐敗のスクープを出したけれども-日本共産党という組織の、様々なまずい対応、もう愚かと言っていい対応を見るにつけ、自民党もそうだが共産党も何か組織的劣化が進んでいるのではないかと考えるに至った。
「除名問題」に関わる諸々は、そう思わせるに十分なほどひどいものだった。併せて大阪、富田林市などのハラスメント問題も見るにつけ、共産党もこれまたあまりにもまずい対応が続いている。
これは何故だろう。
私は「日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと」の中で、共産党というのは実は日本社会の古い部分を忠実に受け継いでいる組織だと感じてそれを指摘した。
それがこのようなまずい対応を生む。
それはとりもなおさず日本社会全般が何か沈下していて、我々はゆっくりと衰退・崩壊への道を進んでいるのではないかという疑念を抱くに十分な状況なのではないか。そう思うのだ。
今大問題になっている大阪万博問題、これは「日本維新の会」問題と言ってもいい事態だろうと思うが、何も自民共産だけではない、政党政治を進める人々全体が、劣化したというか、
社会の進歩に全くついていけていない
だからこそこうしてまずい対応が繰り返される
そのような状況になっているのではないかと思うのだ。そしてそれらの勢力は国政を運営しているのであって、それが日本が世界の中で地盤沈下していく最大の要因にすらなっているのではないか...
さて。
取り留めなく書いたがこれはかなり深刻な状況でもある。このまま我々は沈没し崩壊するのか、それともどこかで再生の道はあるのか。それにしても大きな犠牲を伴うことは避けられないようにも思う。実はすでに犠牲は多く出ているかもしれない。
今後どうなっていくのだろう。先行きは全く見通せない。明るい展望などお世辞にも書くことはできない現状。それが2023年だ。来年はますますひどくなるだろうが、それが安倍政権を放置してきたツケと言えるのだろう。
以下赤旗主張から
主張 松野氏の裏金疑惑 「答え控える」はもう通用せぬ
主張 自民党派閥の裏金 疑惑底なし 政権担う資格ない
ついでに東スポも
田崎史郎氏 安倍派〝疑惑の方程式〟スクープの赤旗に「また赤旗に抜かれてしまった…」
*テレビ番組のまとめみたいな「記事」だが...。なお田「﨑」が正しい
今年の年末は、自民党「安倍派」崩壊の序曲で幕を閉じる。この事件は本当に救いようのない疑獄事件で、「パーティー券」が事実上企業献金の抜け道として使われたのみならず、それが政治資金規正法逃れとして自民党の安部グループが長年利用してきたということである。
言うまでもなく安倍グループは、2012年から長らく政権首班として日本を極めて悪い意味で支配していた人々である。マスコミを支配し、官僚を恫喝し、日本の民主制度を根底から破壊してしまった連中である。
そして森友加計学園問題で公文書の書き換えを行わせ、桜を見る会では政権による私物化を推進、子飼いのジャーナリストによる性犯罪をもみ消すことまでやってのけた政権である。
カルト宗教「統一協会」に野党時代に特に接近し、その支配と拡大を放置どころか一緒になって進めてきたともいえる勢力が自民党、特に安部派である。
「こんな人たち」が日本の政界の中枢にいて日本政治のかじ取りを進めていた。その結果が、日本の経済と世界における位置が徹底的に沈滞したことだ。
その政権をネットでは擁護する意見が大きかったが、それすらも政権が運営していた-Dappi問題でその一端が見えたが-ことすら明らかになった。
そして私を何より絶望的な気分にさせるのは、これらの問題が、2022年夏に安倍晋三が暗殺されてから噴き出した問題ということだ。もちろんモリカケサクラ問題の頃も我々は問題視していたが、マスコミも世論も動きはそれほど大きくはならなかった。
たった一人の人間が殺されたことで、ここまで様々な問題が顕在化して社会問題となっている。いやいや、生きているうちに顕在化しないのは何故なんだ。いったいどうなっているんだ。何なんだこの日本社会は。何かが崩れてしまった。
これは日本の社会状況が極めて非民主的な空気の中で動いていることに他ならないのではないか、私はそう思うのだ。そしてそれらを安倍政権とそれ以降の政権が作り上げてしまった。
安倍政権の犯罪はまさにそのような社会を生んでしまったことにあるようにも思う。
一方...
私はこの間「日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと」として連続で記事を書いた。
*記事表題はアルチュセールのパロディですが
今年の1月から始まった「除名問題」の対応を1年近く見続けてきた。そして-今回自民党金権腐敗のスクープを出したけれども-日本共産党という組織の、様々なまずい対応、もう愚かと言っていい対応を見るにつけ、自民党もそうだが共産党も何か組織的劣化が進んでいるのではないかと考えるに至った。
「除名問題」に関わる諸々は、そう思わせるに十分なほどひどいものだった。併せて大阪、富田林市などのハラスメント問題も見るにつけ、共産党もこれまたあまりにもまずい対応が続いている。
これは何故だろう。
私は「日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと」の中で、共産党というのは実は日本社会の古い部分を忠実に受け継いでいる組織だと感じてそれを指摘した。
それがこのようなまずい対応を生む。
それはとりもなおさず日本社会全般が何か沈下していて、我々はゆっくりと衰退・崩壊への道を進んでいるのではないかという疑念を抱くに十分な状況なのではないか。そう思うのだ。
今大問題になっている大阪万博問題、これは「日本維新の会」問題と言ってもいい事態だろうと思うが、何も自民共産だけではない、政党政治を進める人々全体が、劣化したというか、
社会の進歩に全くついていけていない
だからこそこうしてまずい対応が繰り返される
そのような状況になっているのではないかと思うのだ。そしてそれらの勢力は国政を運営しているのであって、それが日本が世界の中で地盤沈下していく最大の要因にすらなっているのではないか...
さて。
取り留めなく書いたがこれはかなり深刻な状況でもある。このまま我々は沈没し崩壊するのか、それともどこかで再生の道はあるのか。それにしても大きな犠牲を伴うことは避けられないようにも思う。実はすでに犠牲は多く出ているかもしれない。
今後どうなっていくのだろう。先行きは全く見通せない。明るい展望などお世辞にも書くことはできない現状。それが2023年だ。来年はますますひどくなるだろうが、それが安倍政権を放置してきたツケと言えるのだろう。
社内システムをワンオペするということ [雑想]
これ、ちょっと話題になっていて私も読んだんだけど・・・。


え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか?1
かつては情報システムと言えば戦略的な要素があって、そこへ投資をすることが先進的みたいな風潮が、ごく一部だったかもしれないが、あったと思う。
それにかこつけてコスト意識の全くない「情シス」部門があることも私はよく知っている。そんなところを見たことがあるから。
しかし2020年代の今、社内システムってインフラだから、よくわかっていない管理職がコストカットして一時的に自分の評価を引き上げようとする。そんなことがあちこちであるようだ。そんな悲哀を随分ライトに描いているのがこの作品。
まあ、ワンオペしている人に対して普段は-いなくなられると困るから-適当に褒めるんだけど、いざ「何かしなきゃ」という局面になると、こうして目先の成果につられて意味不明なことをする人というのはいるものだと思って読んだ。
うん。

え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか?1
かつては情報システムと言えば戦略的な要素があって、そこへ投資をすることが先進的みたいな風潮が、ごく一部だったかもしれないが、あったと思う。
それにかこつけてコスト意識の全くない「情シス」部門があることも私はよく知っている。そんなところを見たことがあるから。
しかし2020年代の今、社内システムってインフラだから、よくわかっていない管理職がコストカットして一時的に自分の評価を引き上げようとする。そんなことがあちこちであるようだ。そんな悲哀を随分ライトに描いているのがこの作品。
まあ、ワンオペしている人に対して普段は-いなくなられると困るから-適当に褒めるんだけど、いざ「何かしなきゃ」という局面になると、こうして目先の成果につられて意味不明なことをする人というのはいるものだと思って読んだ。
うん。
タグ:ワンオペ
日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと(下) [社会情勢]
共産党でなぜこんな問題が起こっているのだろう。そして何が要因となっているのだろう。
私は共産党員の世代交代ができていないことから見えてくる、党員の任務の多さ、運動の古さ・アップデートのなさがあるのではと思う。
共産党員の高齢化と党員数の急激な減少
日本共産党員は高齢者が多い。というのも最大のボリュームゾーンがいわゆる「団塊の世代」だから。「2025年問題」で知られるようにその世代はもう間もなく全員「後期高齢者」となる。それ以前の70年代の躍進を支えた世代は既に鬼籍に入られたか活動することが困難な人も多い。
それらでは、新しい党員がやってくるのを手ぐすね引いて待っている場所も多くある。
しんぶん赤旗の配布をお願いしたい、ビラ巻きの担当をしてほしい、選挙での電話がけをしてほしい。
新しい人が来ることで、現状を打開したい。その具体的な内容については、よくわからないけれど。
こんなところではないか。
これらを見て、新たに共産党に入って活躍したいという人がいるだろうか。いるとは思う。しかし後期高齢を迎える党員らの活動を補填できるほどの数には決してならない。
そして高齢者ばかりになった組織の世代間ギャップは、組織の拡大には大いに障害になる。それはどこでも同じではあるが。
世代が違うので、そもそも現在の勤労現役世代との意識が違う。雇用や賃金への認識。いわゆる「団塊世代」は倍々で給与が増えた時代を体験している。しかしそれは遠い昔。30年間賃金が上がらないとはそういうことなのだ。
仕事への意識やその強化集中度も世代ごとに大きな差が出ている。現在の社会状況はここ十数年で第2次、3次「産業革命」などと言われるほど違う。10年前の常識すら通じないこともあるのだ。
これらの様々を、仕事を離れて10数年の人たちに認識できるだろうか。共産党員の、会議参加や各種の活動、特に共産党は現在新規党員の獲得と機関紙の拡大を最優先課題として何と3割も増やすことを目標にしている。機関紙の拡大は基本戸別訪問だ。そして選挙活動で必ず発生する「支持拡大」と称する「テレアポ」、「ハンドマイク宣伝」と称する突然の街頭宣伝。これらは1970年代からスタイルがほぼ変わっていないのだ。
これらすっかり古臭くなってしまった行動様式に、新しく共産党に入った人々は、素直に応えられるだろうか。そして党費だ募金だと金がかかることに耐えられるのか…。
共産党の活動にはそれなりの金がかかる
意義は理解できるが活動がなんかちょっと違うなあと思いつつ、しかも事前に聞いていた党費はともかく、○○議員支援募金、○○委員会維持募金、○○事務所募金、春、夏、冬に加えて一時金募金…。
加えて機関紙の購読。赤旗は日刊紙と日曜版。購読しなくてもいいんだけれど、活動内容の最重要な任務は機関紙の拡大だ。拡大する側が「読んでいません」なんて言えないだろう。すると日刊・日曜版で4500円/月。このほかにちょいちょい増刊やパンフレットの金がかかる。
そして傘下団体への加入が要請される。そこは一つ一つの会費は月数百円とかだけれど、その団体が数十もある。全部に入らないにせよその会費も馬鹿にならない。
これら合計すると、一か月あたり下手すると万単位の金がかかる。年間だと10万円以上。年額10万円の収入増が、どれほど困難な道のりかを現役世代は知っている。そんな意識を高齢共産党員たちは、共有できるのだろうか。
党へある意味身も心も捧げなくてはならない、そんな政党に若い人たちは入るのだろうか。
今時は月額数百円のサブスクへの加入を躊躇する時代。岸田現政権が生活援助策として4万とか8万とかを配布する、それへの批判として「月額数千円では何の足しにもならないよ」との意見がある。子育て世代への支援として東京都がようやく来年から始める制度も月5000円。我々はそうして暮らしている。
若い人たちはどう思うかな。必ず払う必要はない、免除制度もあると党は言う。だけれどね。真面目な人ほどそれらの制度を利用すると後ろめたいだろう。ましてや給与所得のある「現役世代」なら、年金生活者の期待の目を気にすることもあろうに。
であれば共産党は何を考えるべきか…は共産党の幹部諸君に任せよう。私は問題提起するだけだ。
大本営体質、というか共産党は昔ながらの、極めて日本的な組織
共産党を批判する人はその「無謬体質」を指摘する。これは特に党中央が持つ「過ちを認めない姿勢」に表れている。過ちをそれとして認めないから、様々な理由をつける。もちろんそれらの理由は組織内では一定の理屈は立つだろうが、党外ではそうはいかない。
これを「続・希望の共産党」で醍醐聡氏が「大本営体質」と評していた。
つまり共産党は誤りを認めず、現実を自らに都合よく変えて自分が正しかったことを喧伝するが、それは各地で敗北する軍に対し「転進」「玉砕」と宣伝したかつての大日本帝国と同じである。これが彼が指摘する「大本営体質」というものだ。


続・希望の共産党 再生を願って
大本営体質というか、私は共産党というのは、いかにもな日本的組織と思う。
共産党、というか共産党の中央委員会はかつて「客観的情勢は熟しているが主体的力量が足りない」としていた。これは「党中央は正しく情勢を認識し正しい方針を出しているのに下部組織に問題がある」ということだ。
さすがにこれでは党組織が弱ると思ったからか、最近では例えば敗北した選挙で「わが党が論戦をリードした」とか「(比較対象にならない選挙を並列して)〇〇選挙と比較してこれだけ前進した」などとやる。
これらはおよそ科学的視点からは遠い内容も多いのが特徴だ。
共産党の候補者にもなっていた大野たかし氏のnote
*現在は離党している。
そして最後には「やり切れば勝てる」という精神論に逃げ込む。精神論は組織のトップが最もとってはいけない戦術だ。
これによく似た組織がある。五ノ井さんらが告発したハラスメント問題で、対応が右往左往している「自衛隊」だ。計画して予算もついたからと止められなくなっている各種の事業。そして予算を大幅に超過し破綻間近の「大阪万博」や、問題噴出の「マイナンバーカード」に象徴される大型公共事業。これらすべて言を左右に誤りを認めずにいる。
会社組織にもそのような傾向があるところも多かろう。そしてそれはオリンパスなどのように時折組織外に問題が立ち現れる。そこに私は昔からの日本の組織風土を見る。「神風特攻」と同じ臭いを感じる。
「日本的」な組織だからハラスメントも起こりうる
実は現在の共産党もこれと構造がよく似ている。つまりは旧来の自民党政府をもっとも批判しているはずの日本共産党は、実に「日本的」な組織なのだ。その行動様式を非常によく「保存」している。
その要因も党員が高齢化し組織的新陳代謝が行われなくなっているために発生している。そうは考えられないだろうか。組織の行動様式とは、その組織構造と密着しているものだ。
そのような組織風土では、セクハラやパワハラといった問題も放置されがちだ。なぜならかつてそれらは問題にならなかったから。
ましてや共産党という組織の中では、問題を外に持ち出さないという風潮がある。それは正に今回松竹氏、鈴木氏が除名されたことに典型的に表れている。ハラスメントが起こる組織は例外なく組織内での浄化作用がない。しかし問題を組織外に持ち出せないということは、被害者に「黙れ」と言っているに等しいのだ。
この間噴出している各種の問題は、旧来の共産党員が持つ保守性や暴力性が、新規に入ってきた、特に若い共産党員へのハラスメントとして現れる事案が多いように私は感じる。これらは今始まったものではなくかつては問題として見えにくかったが、SNS全盛の時代となり拡散されやすくなった。かつ声を上げる被害者が多くなってもいることが影響しているのだろう。
党員の老齢化と保守化がそれに拍車をかけていると考えるのは、私の邪推には止まらないだろう。
加えていうならば、旧日本軍はダメージコントロールがものすごく下手だった。撤退戦もダメだった。共産党の「除名問題」に関わる党中央の対応と支持者らのTwitterでの発言は、それを思い起こさせるに十分なひどさだった。そこにも私は共産党と大日本帝国との共通性を見るのである。
そして共産党員の高齢化と軌を一にして発生しているのが共産党系組織の「保守化」である。
共産党員の「保守化」と「共産党エコシステム」
私は共産党員の世代交代ができていないことから見えてくる、党員の任務の多さ、運動の古さ・アップデートのなさがあるのではと思う。
共産党員の高齢化と党員数の急激な減少
日本共産党員は高齢者が多い。というのも最大のボリュームゾーンがいわゆる「団塊の世代」だから。「2025年問題」で知られるようにその世代はもう間もなく全員「後期高齢者」となる。それ以前の70年代の躍進を支えた世代は既に鬼籍に入られたか活動することが困難な人も多い。
それらでは、新しい党員がやってくるのを手ぐすね引いて待っている場所も多くある。
しんぶん赤旗の配布をお願いしたい、ビラ巻きの担当をしてほしい、選挙での電話がけをしてほしい。
新しい人が来ることで、現状を打開したい。その具体的な内容については、よくわからないけれど。
こんなところではないか。
これらを見て、新たに共産党に入って活躍したいという人がいるだろうか。いるとは思う。しかし後期高齢を迎える党員らの活動を補填できるほどの数には決してならない。
そして高齢者ばかりになった組織の世代間ギャップは、組織の拡大には大いに障害になる。それはどこでも同じではあるが。
世代が違うので、そもそも現在の勤労現役世代との意識が違う。雇用や賃金への認識。いわゆる「団塊世代」は倍々で給与が増えた時代を体験している。しかしそれは遠い昔。30年間賃金が上がらないとはそういうことなのだ。
仕事への意識やその強化集中度も世代ごとに大きな差が出ている。現在の社会状況はここ十数年で第2次、3次「産業革命」などと言われるほど違う。10年前の常識すら通じないこともあるのだ。
これらの様々を、仕事を離れて10数年の人たちに認識できるだろうか。共産党員の、会議参加や各種の活動、特に共産党は現在新規党員の獲得と機関紙の拡大を最優先課題として何と3割も増やすことを目標にしている。機関紙の拡大は基本戸別訪問だ。そして選挙活動で必ず発生する「支持拡大」と称する「テレアポ」、「ハンドマイク宣伝」と称する突然の街頭宣伝。これらは1970年代からスタイルがほぼ変わっていないのだ。
これらすっかり古臭くなってしまった行動様式に、新しく共産党に入った人々は、素直に応えられるだろうか。そして党費だ募金だと金がかかることに耐えられるのか…。
共産党の活動にはそれなりの金がかかる
意義は理解できるが活動がなんかちょっと違うなあと思いつつ、しかも事前に聞いていた党費はともかく、○○議員支援募金、○○委員会維持募金、○○事務所募金、春、夏、冬に加えて一時金募金…。
加えて機関紙の購読。赤旗は日刊紙と日曜版。購読しなくてもいいんだけれど、活動内容の最重要な任務は機関紙の拡大だ。拡大する側が「読んでいません」なんて言えないだろう。すると日刊・日曜版で4500円/月。このほかにちょいちょい増刊やパンフレットの金がかかる。
そして傘下団体への加入が要請される。そこは一つ一つの会費は月数百円とかだけれど、その団体が数十もある。全部に入らないにせよその会費も馬鹿にならない。
これら合計すると、一か月あたり下手すると万単位の金がかかる。年間だと10万円以上。年額10万円の収入増が、どれほど困難な道のりかを現役世代は知っている。そんな意識を高齢共産党員たちは、共有できるのだろうか。
党へある意味身も心も捧げなくてはならない、そんな政党に若い人たちは入るのだろうか。
今時は月額数百円のサブスクへの加入を躊躇する時代。岸田現政権が生活援助策として4万とか8万とかを配布する、それへの批判として「月額数千円では何の足しにもならないよ」との意見がある。子育て世代への支援として東京都がようやく来年から始める制度も月5000円。我々はそうして暮らしている。
若い人たちはどう思うかな。必ず払う必要はない、免除制度もあると党は言う。だけれどね。真面目な人ほどそれらの制度を利用すると後ろめたいだろう。ましてや給与所得のある「現役世代」なら、年金生活者の期待の目を気にすることもあろうに。
であれば共産党は何を考えるべきか…は共産党の幹部諸君に任せよう。私は問題提起するだけだ。
大本営体質、というか共産党は昔ながらの、極めて日本的な組織
共産党を批判する人はその「無謬体質」を指摘する。これは特に党中央が持つ「過ちを認めない姿勢」に表れている。過ちをそれとして認めないから、様々な理由をつける。もちろんそれらの理由は組織内では一定の理屈は立つだろうが、党外ではそうはいかない。
これを「続・希望の共産党」で醍醐聡氏が「大本営体質」と評していた。
つまり共産党は誤りを認めず、現実を自らに都合よく変えて自分が正しかったことを喧伝するが、それは各地で敗北する軍に対し「転進」「玉砕」と宣伝したかつての大日本帝国と同じである。これが彼が指摘する「大本営体質」というものだ。

続・希望の共産党 再生を願って
大本営体質というか、私は共産党というのは、いかにもな日本的組織と思う。
共産党、というか共産党の中央委員会はかつて「客観的情勢は熟しているが主体的力量が足りない」としていた。これは「党中央は正しく情勢を認識し正しい方針を出しているのに下部組織に問題がある」ということだ。
さすがにこれでは党組織が弱ると思ったからか、最近では例えば敗北した選挙で「わが党が論戦をリードした」とか「(比較対象にならない選挙を並列して)〇〇選挙と比較してこれだけ前進した」などとやる。
これらはおよそ科学的視点からは遠い内容も多いのが特徴だ。
共産党の候補者にもなっていた大野たかし氏のnote
*現在は離党している。
そして最後には「やり切れば勝てる」という精神論に逃げ込む。精神論は組織のトップが最もとってはいけない戦術だ。
これによく似た組織がある。五ノ井さんらが告発したハラスメント問題で、対応が右往左往している「自衛隊」だ。計画して予算もついたからと止められなくなっている各種の事業。そして予算を大幅に超過し破綻間近の「大阪万博」や、問題噴出の「マイナンバーカード」に象徴される大型公共事業。これらすべて言を左右に誤りを認めずにいる。
会社組織にもそのような傾向があるところも多かろう。そしてそれはオリンパスなどのように時折組織外に問題が立ち現れる。そこに私は昔からの日本の組織風土を見る。「神風特攻」と同じ臭いを感じる。
「日本的」な組織だからハラスメントも起こりうる
実は現在の共産党もこれと構造がよく似ている。つまりは旧来の自民党政府をもっとも批判しているはずの日本共産党は、実に「日本的」な組織なのだ。その行動様式を非常によく「保存」している。
その要因も党員が高齢化し組織的新陳代謝が行われなくなっているために発生している。そうは考えられないだろうか。組織の行動様式とは、その組織構造と密着しているものだ。
そのような組織風土では、セクハラやパワハラといった問題も放置されがちだ。なぜならかつてそれらは問題にならなかったから。
ましてや共産党という組織の中では、問題を外に持ち出さないという風潮がある。それは正に今回松竹氏、鈴木氏が除名されたことに典型的に表れている。ハラスメントが起こる組織は例外なく組織内での浄化作用がない。しかし問題を組織外に持ち出せないということは、被害者に「黙れ」と言っているに等しいのだ。
この間噴出している各種の問題は、旧来の共産党員が持つ保守性や暴力性が、新規に入ってきた、特に若い共産党員へのハラスメントとして現れる事案が多いように私は感じる。これらは今始まったものではなくかつては問題として見えにくかったが、SNS全盛の時代となり拡散されやすくなった。かつ声を上げる被害者が多くなってもいることが影響しているのだろう。
党員の老齢化と保守化がそれに拍車をかけていると考えるのは、私の邪推には止まらないだろう。
加えていうならば、旧日本軍はダメージコントロールがものすごく下手だった。撤退戦もダメだった。共産党の「除名問題」に関わる党中央の対応と支持者らのTwitterでの発言は、それを思い起こさせるに十分なひどさだった。そこにも私は共産党と大日本帝国との共通性を見るのである。
そして共産党員の高齢化と軌を一にして発生しているのが共産党系組織の「保守化」である。
共産党員の「保守化」と「共産党エコシステム」
日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと(中の2) [社会情勢]
日本共産党への論考を進めようとあれこれ考えていたら、早2か月。そして驚愕の出来事が発生した。
共産党福岡市議団事務局長の神谷貴行氏(ペンネーム紙屋高雪で有名)が処分の憂き目にあっているという。
彼もまた自身のBlogで極めて穏当な意見を書いただけ、しかも東大で学生運動上がりらしい緻密で共産党中央からにらまれないよう自己主張をするという内容であった。
それなのに。
かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
*2018年の福岡市長選立候補にあたって開設したと思われるが、現在まで継続して更新しているBlogは珍しい。落選するとそれで終わりという候補者のサイトは共産党に限らず数多くある。
紙屋高雪氏のBlog「紙屋研究所」
さて、今回紹介した各種の「事件」は、今年になって大きな問題として発覚したものだ。それは当事者がネットで発信したからという点が大きい。ネットで発信していなければ、当事者以外に知られることなく消え去っていたことだろう。
蛭子議員は赤旗等で報道される「除名」ではなく、党員としての資格がない場合に処理される「除籍」だった。この場合ひっそりと処理され、世間はおろか当の本人すら知らないという事態もありうるのだ。
*オウムや統一協会批判の論客として知られる有田芳生元参院議員も、自身が除籍されて等を追われたことを知ったのは、処分から半年後、自身で党に質問してからであった。
では、最近になって共産党内でこうした問題が多くなってきたのだろうか。
どうもそうではないのである。
例えば・・・
5人もいた議員団が崩壊し、たった1期でわずか1名しかいなくなってしまった共産党埼玉県草加市の事件(2019年)
抗議の離党をした3名のうちの1名、佐藤のりかず市議会議員による経過説明
事件の渦中で除籍させられ、のち病死した草加市委員長、中島束(なかじまつかね)氏のBlog
岐阜県岐阜市でパワハラを理由に共産党議員が離党し会派離脱した事件(2018年)
当時の共産党岐阜県委員会の声明
*当初、原議員は議員を引退するとの情報もあったが、現在も無所属議員として活動されている
埼玉県所沢市で共産党市議がパワハラ被害で離党(2020年)
この直前にベテラン議員もセクハラで議員辞職している。なおパワハラ被害の議員は2023年選挙で落選。
そして何より私の住む立川市のおとなり、日野市でも共産党議員が離党していた(2017年)
経緯としては5年以上前からの案件のようである。ここでも共産党の各地方組織による強引な「指導」があった。ハラスメントと言ってもいい。
当事者の奥野りん子議員
*離党後も現職の市議会議員である
最近ではやはりお隣の国立市で、30代の新人議員がわずか一期で議員を降りてしまった。代わった60代の新人候補は落選。国立の共産党市議はわずか2人になってしまった。1999年までは6人もいたのに。
同様にお隣の国分寺市でも、かつて5人いた共産党議員は2023年にとうとう1人になってしまった。
なぜこのようなことになってしまったのだろうか。
日本共産党には多くの課題がある(いったん中断。今度こそ「下」に続く)
共産党福岡市議団事務局長の神谷貴行氏(ペンネーム紙屋高雪で有名)が処分の憂き目にあっているという。
彼もまた自身のBlogで極めて穏当な意見を書いただけ、しかも東大で学生運動上がりらしい緻密で共産党中央からにらまれないよう自己主張をするという内容であった。
それなのに。
かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
*2018年の福岡市長選立候補にあたって開設したと思われるが、現在まで継続して更新しているBlogは珍しい。落選するとそれで終わりという候補者のサイトは共産党に限らず数多くある。
紙屋高雪氏のBlog「紙屋研究所」
さて、今回紹介した各種の「事件」は、今年になって大きな問題として発覚したものだ。それは当事者がネットで発信したからという点が大きい。ネットで発信していなければ、当事者以外に知られることなく消え去っていたことだろう。
蛭子議員は赤旗等で報道される「除名」ではなく、党員としての資格がない場合に処理される「除籍」だった。この場合ひっそりと処理され、世間はおろか当の本人すら知らないという事態もありうるのだ。
*オウムや統一協会批判の論客として知られる有田芳生元参院議員も、自身が除籍されて等を追われたことを知ったのは、処分から半年後、自身で党に質問してからであった。
では、最近になって共産党内でこうした問題が多くなってきたのだろうか。
どうもそうではないのである。
例えば・・・
5人もいた議員団が崩壊し、たった1期でわずか1名しかいなくなってしまった共産党埼玉県草加市の事件(2019年)
抗議の離党をした3名のうちの1名、佐藤のりかず市議会議員による経過説明
事件の渦中で除籍させられ、のち病死した草加市委員長、中島束(なかじまつかね)氏のBlog
岐阜県岐阜市でパワハラを理由に共産党議員が離党し会派離脱した事件(2018年)
当時の共産党岐阜県委員会の声明
*当初、原議員は議員を引退するとの情報もあったが、現在も無所属議員として活動されている
埼玉県所沢市で共産党市議がパワハラ被害で離党(2020年)
この直前にベテラン議員もセクハラで議員辞職している。なおパワハラ被害の議員は2023年選挙で落選。
そして何より私の住む立川市のおとなり、日野市でも共産党議員が離党していた(2017年)
経緯としては5年以上前からの案件のようである。ここでも共産党の各地方組織による強引な「指導」があった。ハラスメントと言ってもいい。
当事者の奥野りん子議員
*離党後も現職の市議会議員である
最近ではやはりお隣の国立市で、30代の新人議員がわずか一期で議員を降りてしまった。代わった60代の新人候補は落選。国立の共産党市議はわずか2人になってしまった。1999年までは6人もいたのに。
同様にお隣の国分寺市でも、かつて5人いた共産党議員は2023年にとうとう1人になってしまった。
なぜこのようなことになってしまったのだろうか。
日本共産党には多くの課題がある(いったん中断。今度こそ「下」に続く)
タグ:日本共産党
日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと(中) [社会情勢]
田平まゆみ議員と岡田ひでき議員の事案
田平まゆみ元議員のTwitter
田平まゆみ元議員のfacebook
富田林市議会は2019年改選時点で定数18名の中、共産党議員が2名。議員4期目の岡田英樹氏、議員2期目の田平まゆみ氏の両名である。改選前はベテランの議員がいたが、世代交代で新人にしたところ新人が落選し3名中2名の当選、という経過のようだ。
ハラスメント被害を訴えている田平氏によると、田平氏2期目、つまり2019年から岡田氏によるハラスメントが始まった。
内容は典型的(いわゆる「パワハラ」)で日常的に「おまえ」「あいつ」と呼ぶ、他議員に田平氏の悪口を言う、会議日程を伝えず無断欠席したように見せる、街頭演説中に大声で田平氏に「指示」する等々である。
2023年2月下旬付の「日本共産党大阪府常任委員会」の文書からみると、上記の件に関して田平氏は共産党の地区委員会や大阪府委員会、中央委員会に被害の訴えをしていたようだ。しかし党はなかなか動こうとせず、ようやく2022年11月26日に田平氏にヒアリングし、岡田氏と関係者へ調査を行ったとのこと。
この時点で田平氏は自身のTwitterでハラスメントに関する情報を発信し始める。内容は共産党に敵対するものではなく、あくまで真実を明らかにするという態度であった。共産党員と思われるアカウントも、多くは彼女を支持しているようだった(*)。
岡田氏は田平氏のみにとどまらず、他党議員らにも同様のハラスメント発言を繰り返しており、かつ田平氏へのハラスメント行為は他の党員も見聞きしており、調査で改めてそれが明らかになっている。
文書によれば「岡田市議は反省を深めています」とのことである。
(*)後に分かったことだが、共産党中央の見解を垂れ流すアカウントの複数が、田平氏ではなく岡田氏の肩を持っていることも明らかになった
そして共産党は岡田氏によるハラスメント行為を認定し、岡田氏は自ら共産党の役職を降りた。田平氏によれば、共産党は彼の市議候補公認をしない、無所属での出馬も当然認められない、ということが伝えられたとのことである。
ここまでは時間がかかったとはいえ、まあいいとしよう。
その後3月末に岡田氏は共産党を離党してしまった。田平氏によれば離党した岡田氏が無所属で出馬することになっても、共産党組織は支援しないとのことであった。
その後である。
田平氏は議員候補になれなかった
2023年4月の統一地方選、富田林市は定数18のまま、日本共産党は候補者を一人しか立てなかった。新人の寺尾氏である。
富田林市は落選したとはいえ、前回選挙で3名の候補を立て、かつ前々回(定数19名だが)までは3名の議員がいたのである。それが今回公認が1名。
しかも田平氏は議員継続の意思があった。それをTwitterでも公言していたし、共産党の地区委員会にも伝えていた。
前回の富田林市での選挙結果を見てみよう。
2019年4月21日 富田林市議会議員一般選挙
票数・候補者名・得票順位
1848・田平まゆみ・13位
1509・岡田ひでき・15位
886・川﨑よしき・19位:落選
2015年4月26日 同選挙
票数・候補者名・得票順位
1723・岡田英樹・14位
1634・田平まゆみ・16位
1630・奥田良久・17位
2011年4月24日 同選挙
票数・候補者名・得票順位
1833・上原幸子・15位
1822・岡田英樹・17位
1730・奥田良久・19位
過去3回を振り返ると、岡田氏および共産党全体が票を減らす中、田平氏は着実に得票数を増やしていることがわかる。
つまりは候補者として「試されずみ(共産党用語ですこれ)」なのは田平氏であると言えよう。
しかし富田林の共産党は何をしたか。
田平氏を意識的に組織から外す
2023年1月、共産党はあちこちで「新春のつどい」というものを行う。統一地方選の年なので、多くはこの場で議員の候補者をお披露目するのだが、なんとその場で候補者にならないはずの岡田氏が候補者として紹介された。またもう一名は田平氏ではなく新人候補であった。
田平氏にはこのことは全く知らされていなかった。
田平氏はこれに抗議し、同年2月に大阪の共産党はこれに対しても「誤った判断」であり「深く反省」し「心から謝罪」した。
しかし立候補の意思があるにもかかわらず、3名当選させるだけの力量があるにもかかわらず、富田林市の共産党は市議候補を新人の寺尾氏のみ公認とした。
あきれたハラスメント加害者
岡田氏はというと共産党を離れ無所属議員となり、4月の選挙には無所属で立候補することになった。
そして彼が候補者活動を始めた4月初旬、驚くべきことが現地の共産党関係者によって明らかになった。
・岡田氏の選挙事務所は、富田林市の「生活と健康を守る会(共産党に近い組織)」と同じ建物
・岡田氏の選挙事務所横断幕の下には、富田林市の「新日本婦人の会(これも共産党に近い組織)」の横断幕がもともとあり、彼の横断幕で隠されていた
・現地の地区委員会で寺尾氏の活動地域と、離党したはずの岡田氏の地域が設定された地図が張り出されていた
・岡田氏の立候補第一声には、岡田氏を支援する共産党員や支持者が集まっていた
・立候補演説で岡田氏は「パワハラはとんでもないデマ」「マスコミで、新聞にもウソの報道が一方的に載せられた」「いろんなデマを流されてマスコミもそれに乗っかって報道するという変な事態の中で起こっている選挙」と明言した
そして選挙 岡田氏の落選
2023年4月23日、富田林市市議会議員選挙の結果である。共産党の寺尾氏は2119票で6位。岡田氏は前回よりさらに減らして1246票であった。
彼は最下位同数でくじ引きとなり、あえなく落選した。「お天道様は見ているぞ」という言葉にふさわしい結果であった。
富田林市の共産党得票数は岡田氏の票も入れると3365票。得票率8.5%と前回より14%も減らす惨敗であった。(もちろん岡田氏は無所属候補なので、純粋な共産党票はもっと少ない)
田平氏のTwitterによれば、選挙後、富田林市の共産党の会議で参加者から「岡田さん通せず残念」「通ればわだかまりは無くなった」「今回のやり方は良い例」「中央委員会や府委員会から岡田支援は処分されないと確認した。会派を組む事もあれほど約束した」との発言があったとのこと。
自ら党の体力を減らして、彼らは何も反省していないのである。
そして5月。落選した岡田氏は、印刷会社に依頼し『"パワハラ問題"の「経緯」と「真相」』なるものを1000部も印刷し、支持者らに配布した。その内容はこの間の「反省」や「謝罪」など全くなかったかのように、パワハラなどしておらず田平氏に問題があると、自身の正当化するだけのものであった。
この文書は7月に田平氏も入手してTwitterで公開し、全国に明らかになったのである。
岡田氏のハラスメント隠蔽文書を明らかにした田平氏のツイート
田平まゆみ元議員のTwitter
田平まゆみ元議員のfacebook
富田林市議会は2019年改選時点で定数18名の中、共産党議員が2名。議員4期目の岡田英樹氏、議員2期目の田平まゆみ氏の両名である。改選前はベテランの議員がいたが、世代交代で新人にしたところ新人が落選し3名中2名の当選、という経過のようだ。
ハラスメント被害を訴えている田平氏によると、田平氏2期目、つまり2019年から岡田氏によるハラスメントが始まった。
内容は典型的(いわゆる「パワハラ」)で日常的に「おまえ」「あいつ」と呼ぶ、他議員に田平氏の悪口を言う、会議日程を伝えず無断欠席したように見せる、街頭演説中に大声で田平氏に「指示」する等々である。
2023年2月下旬付の「日本共産党大阪府常任委員会」の文書からみると、上記の件に関して田平氏は共産党の地区委員会や大阪府委員会、中央委員会に被害の訴えをしていたようだ。しかし党はなかなか動こうとせず、ようやく2022年11月26日に田平氏にヒアリングし、岡田氏と関係者へ調査を行ったとのこと。
この時点で田平氏は自身のTwitterでハラスメントに関する情報を発信し始める。内容は共産党に敵対するものではなく、あくまで真実を明らかにするという態度であった。共産党員と思われるアカウントも、多くは彼女を支持しているようだった(*)。
岡田氏は田平氏のみにとどまらず、他党議員らにも同様のハラスメント発言を繰り返しており、かつ田平氏へのハラスメント行為は他の党員も見聞きしており、調査で改めてそれが明らかになっている。
文書によれば「岡田市議は反省を深めています」とのことである。
(*)後に分かったことだが、共産党中央の見解を垂れ流すアカウントの複数が、田平氏ではなく岡田氏の肩を持っていることも明らかになった
そして共産党は岡田氏によるハラスメント行為を認定し、岡田氏は自ら共産党の役職を降りた。田平氏によれば、共産党は彼の市議候補公認をしない、無所属での出馬も当然認められない、ということが伝えられたとのことである。
ここまでは時間がかかったとはいえ、まあいいとしよう。
その後3月末に岡田氏は共産党を離党してしまった。田平氏によれば離党した岡田氏が無所属で出馬することになっても、共産党組織は支援しないとのことであった。
その後である。
田平氏は議員候補になれなかった
2023年4月の統一地方選、富田林市は定数18のまま、日本共産党は候補者を一人しか立てなかった。新人の寺尾氏である。
富田林市は落選したとはいえ、前回選挙で3名の候補を立て、かつ前々回(定数19名だが)までは3名の議員がいたのである。それが今回公認が1名。
しかも田平氏は議員継続の意思があった。それをTwitterでも公言していたし、共産党の地区委員会にも伝えていた。
前回の富田林市での選挙結果を見てみよう。
2019年4月21日 富田林市議会議員一般選挙
票数・候補者名・得票順位
1848・田平まゆみ・13位
1509・岡田ひでき・15位
886・川﨑よしき・19位:落選
2015年4月26日 同選挙
票数・候補者名・得票順位
1723・岡田英樹・14位
1634・田平まゆみ・16位
1630・奥田良久・17位
2011年4月24日 同選挙
票数・候補者名・得票順位
1833・上原幸子・15位
1822・岡田英樹・17位
1730・奥田良久・19位
過去3回を振り返ると、岡田氏および共産党全体が票を減らす中、田平氏は着実に得票数を増やしていることがわかる。
つまりは候補者として「試されずみ(共産党用語ですこれ)」なのは田平氏であると言えよう。
しかし富田林の共産党は何をしたか。
田平氏を意識的に組織から外す
2023年1月、共産党はあちこちで「新春のつどい」というものを行う。統一地方選の年なので、多くはこの場で議員の候補者をお披露目するのだが、なんとその場で候補者にならないはずの岡田氏が候補者として紹介された。またもう一名は田平氏ではなく新人候補であった。
田平氏にはこのことは全く知らされていなかった。
田平氏はこれに抗議し、同年2月に大阪の共産党はこれに対しても「誤った判断」であり「深く反省」し「心から謝罪」した。
しかし立候補の意思があるにもかかわらず、3名当選させるだけの力量があるにもかかわらず、富田林市の共産党は市議候補を新人の寺尾氏のみ公認とした。
あきれたハラスメント加害者
岡田氏はというと共産党を離れ無所属議員となり、4月の選挙には無所属で立候補することになった。
そして彼が候補者活動を始めた4月初旬、驚くべきことが現地の共産党関係者によって明らかになった。
・岡田氏の選挙事務所は、富田林市の「生活と健康を守る会(共産党に近い組織)」と同じ建物
・岡田氏の選挙事務所横断幕の下には、富田林市の「新日本婦人の会(これも共産党に近い組織)」の横断幕がもともとあり、彼の横断幕で隠されていた
・現地の地区委員会で寺尾氏の活動地域と、離党したはずの岡田氏の地域が設定された地図が張り出されていた
・岡田氏の立候補第一声には、岡田氏を支援する共産党員や支持者が集まっていた
・立候補演説で岡田氏は「パワハラはとんでもないデマ」「マスコミで、新聞にもウソの報道が一方的に載せられた」「いろんなデマを流されてマスコミもそれに乗っかって報道するという変な事態の中で起こっている選挙」と明言した
そして選挙 岡田氏の落選
2023年4月23日、富田林市市議会議員選挙の結果である。共産党の寺尾氏は2119票で6位。岡田氏は前回よりさらに減らして1246票であった。
彼は最下位同数でくじ引きとなり、あえなく落選した。「お天道様は見ているぞ」という言葉にふさわしい結果であった。
富田林市の共産党得票数は岡田氏の票も入れると3365票。得票率8.5%と前回より14%も減らす惨敗であった。(もちろん岡田氏は無所属候補なので、純粋な共産党票はもっと少ない)
田平氏のTwitterによれば、選挙後、富田林市の共産党の会議で参加者から「岡田さん通せず残念」「通ればわだかまりは無くなった」「今回のやり方は良い例」「中央委員会や府委員会から岡田支援は処分されないと確認した。会派を組む事もあれほど約束した」との発言があったとのこと。
自ら党の体力を減らして、彼らは何も反省していないのである。
そして5月。落選した岡田氏は、印刷会社に依頼し『"パワハラ問題"の「経緯」と「真相」』なるものを1000部も印刷し、支持者らに配布した。その内容はこの間の「反省」や「謝罪」など全くなかったかのように、パワハラなどしておらず田平氏に問題があると、自身の正当化するだけのものであった。
この文書は7月に田平氏も入手してTwitterで公開し、全国に明らかになったのである。
岡田氏のハラスメント隠蔽文書を明らかにした田平氏のツイート
日本共産党の中でこれ以上続いてはいけないこと(上) [社会情勢]
日本共産党内がガタガタに揺れている。
年明けの松竹伸幸、鈴木元両氏の党中央批判とそれを理由にした除名の後、彼らに賛同しTwitterやFacebookで声を上げた、兵庫県南あわじ市の蛭子智彦議員の機関役員の罷免と除籍処分が発生した。
また2019年から党内でのハラスメント(パワハラ)を訴え続けている、大阪府富田林市の田平まゆみ議員(当時)と、ハラッサーである岡田ひでき議員(当時)について、今年2023年になって共産党内での不可解な動きがあった。「事件」としてもよい。
蛭子智彦議員の事案
蛭子智彦議員のTwitter
蛭子議員のfacebook
1月くらいから、松竹氏と鈴木氏への共感を口にしていた蛭子氏だったが、発言自体は温厚なものではあった。私と自衛隊に関する見解は異なるが、議員らしい理性ある対応を批判者に対して続けていた。
すると党中央を妄信するアカウント数名が蛭子氏に絡みつき「離党しろ」などの悪罵を投げつけていた。そのうちの一人に至っては、蛭子氏が(地元の偉人)大内兵衛を尊敬していると書いていることに難癖をつけ(1930年代の左翼間であった)講座派と労農派の論争で大内が労農派であったことを根拠に「共産党員にはふさわしくない」などの暴言を吐く始末であった。
こうした中で2月上旬、蛭子氏は共産党員としての「権利制限」という処分を受けた。それがそのまま3か月にわたり放置され、3月末に共産党南あわじ議員団の解消が決まった。解消を求めたのは蛭子氏。会議不参加の権利制限中では活動ができないとの判断のようである。
その後5月半ばに蛭子氏が支部長を務める、共産党の影響が強い「治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟」の役職を、党員からの強い反対により降りざるを得なくなった。ここで彼は共産党離党を決意する。そして離党届を出したが受け付けられず、6月初旬になって共産党の地方組織は蛭子氏の党機関の役職罷免という処分の後、共産党を除籍とした。議員辞職も求めたが、蛭子氏は拒否している。
これらの経過について共産党の小池晃書記局長は定例記者会見で以下の引用の通り発言している。
令和の日本共産党ウォッチャーBlog
「蛭子氏は、除名された元党員の主張に同調して、その主張をSNSに投稿して、その後、市議なんですが、会派を離脱して離党表明をしたんですね。」
上記の経過の通り、事実は3月末の段階で、権利制限処分中のため同一会派での活動が困難になったため会派を解消したのであり、離党も度重なる党内での嫌がらせもあり、最終的には所属組織内の党員から市民団体の長を辞めさせられ、それが離党につながったのである。
会派解消については、治安維持法国賠同盟の支部長辞任についての蛭子氏の経過が参考になる。「国賠同盟で党員間で私への態度が3つに分かれて、現職党の議員と元職議員の2人が共産党に背く者は役員退任、同盟退会を主張した」と蛭子氏が記載している。同僚議員が拒否的反応をしたのだろう。どちらに責任があるかと言えば共産党側ではないか。
不可解なTwitter
不可解なことに、Twitterを見ると、5月後半の蛭子氏がまだ離党を言い出していない時期に、突如として党中央を支持する立場からのツイートが増え、蛭子氏に罵声を浴びせている。もちろん彼の支持者も多いので意見としては少数ではあったが。
それらのアカウントに「共産党員として恥ずかしいのでは」と批判する意見が書かれると「私は共産党員ではありません」という返事が返ってくる。
繰り返すがこれもまた不可解な点である。(続く)
年明けの松竹伸幸、鈴木元両氏の党中央批判とそれを理由にした除名の後、彼らに賛同しTwitterやFacebookで声を上げた、兵庫県南あわじ市の蛭子智彦議員の機関役員の罷免と除籍処分が発生した。
また2019年から党内でのハラスメント(パワハラ)を訴え続けている、大阪府富田林市の田平まゆみ議員(当時)と、ハラッサーである岡田ひでき議員(当時)について、今年2023年になって共産党内での不可解な動きがあった。「事件」としてもよい。
蛭子智彦議員の事案
蛭子智彦議員のTwitter
蛭子議員のfacebook
1月くらいから、松竹氏と鈴木氏への共感を口にしていた蛭子氏だったが、発言自体は温厚なものではあった。私と自衛隊に関する見解は異なるが、議員らしい理性ある対応を批判者に対して続けていた。
すると党中央を妄信するアカウント数名が蛭子氏に絡みつき「離党しろ」などの悪罵を投げつけていた。そのうちの一人に至っては、蛭子氏が(地元の偉人)大内兵衛を尊敬していると書いていることに難癖をつけ(1930年代の左翼間であった)講座派と労農派の論争で大内が労農派であったことを根拠に「共産党員にはふさわしくない」などの暴言を吐く始末であった。
こうした中で2月上旬、蛭子氏は共産党員としての「権利制限」という処分を受けた。それがそのまま3か月にわたり放置され、3月末に共産党南あわじ議員団の解消が決まった。解消を求めたのは蛭子氏。会議不参加の権利制限中では活動ができないとの判断のようである。
その後5月半ばに蛭子氏が支部長を務める、共産党の影響が強い「治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟」の役職を、党員からの強い反対により降りざるを得なくなった。ここで彼は共産党離党を決意する。そして離党届を出したが受け付けられず、6月初旬になって共産党の地方組織は蛭子氏の党機関の役職罷免という処分の後、共産党を除籍とした。議員辞職も求めたが、蛭子氏は拒否している。
これらの経過について共産党の小池晃書記局長は定例記者会見で以下の引用の通り発言している。
令和の日本共産党ウォッチャーBlog
「蛭子氏は、除名された元党員の主張に同調して、その主張をSNSに投稿して、その後、市議なんですが、会派を離脱して離党表明をしたんですね。」
上記の経過の通り、事実は3月末の段階で、権利制限処分中のため同一会派での活動が困難になったため会派を解消したのであり、離党も度重なる党内での嫌がらせもあり、最終的には所属組織内の党員から市民団体の長を辞めさせられ、それが離党につながったのである。
会派解消については、治安維持法国賠同盟の支部長辞任についての蛭子氏の経過が参考になる。「国賠同盟で党員間で私への態度が3つに分かれて、現職党の議員と元職議員の2人が共産党に背く者は役員退任、同盟退会を主張した」と蛭子氏が記載している。同僚議員が拒否的反応をしたのだろう。どちらに責任があるかと言えば共産党側ではないか。
不可解なTwitter
不可解なことに、Twitterを見ると、5月後半の蛭子氏がまだ離党を言い出していない時期に、突如として党中央を支持する立場からのツイートが増え、蛭子氏に罵声を浴びせている。もちろん彼の支持者も多いので意見としては少数ではあったが。
それらのアカウントに「共産党員として恥ずかしいのでは」と批判する意見が書かれると「私は共産党員ではありません」という返事が返ってくる。
繰り返すがこれもまた不可解な点である。(続く)
新聞の、読者投稿欄のこと [雑想]
私はもう40年以上新聞を読んでいる。子どもの頃から自宅には新聞があって、それをざっくり読む癖ができた。一人暮らしをするようになった18歳からは新聞を自分で購読し、よく読んでいた。それは今でも変わらない。
ここ10年位からは、読者投稿に目を向けることが多くなった。いわゆる「投稿欄」には多くの無名な人々の投稿が掲載され、時にさりげなく有名人が投稿もしていたりする。SNS時代になってからは、時々投稿が引用され拡散されるようにもなった。
もう5年前になる。
毎年同じ日に投稿していた早乙女勝元氏
「妻が願った最後の『七日間』」2018年3月9日朝日新聞
朝日新聞に掲載された「1月中旬、妻容子が他界しました。入院ベッドの枕元のノートに『七日間』と題した詩を残して。」から始まる、この非常に切ない内容の投稿はあっという間に大バズリし、書籍にもなったと聞く。この投稿は3月9日朝刊だったが、そのすぐ下の欄には、早乙女勝元氏の投稿「3月10日に消えた声を語り継ぐ」が載っている。つい最近鬼籍に入られた早乙女さんは、ライフワークとなった東京大空襲を語り継ぐために、毎年3月10日付近に朝日新聞に投書を寄せるのだ。そしてそれを同紙は毎年掲載し続けた。
有名人の意外なエピソードが、当時を知る人々によって語られることもある。
「『お色気』大切 加古さんの一言」2019年3月24日赤旗日曜版
この日のしんぶん赤旗日曜版の読者コーナー「人生のうた」には1959年に創刊された日曜版と絵本作家のかこさとし氏のエピソードが載っている。
創刊号に掲載されたブリジット・バルドーをみた当時30代だったかこさとし氏が「共産党さんも考えましたね。お色気というのは大切ですよ。私たちもみんなバルドーさんのこと知ってるじゃないか」と話して大笑いになったことが紹介されている。
「人生のうた」は比較的高齢の投稿者が多く、考えさせられる内容も多い。
「50銭札盗んで女の子に渡す」2017年10月29日赤旗日曜版
戦後避難先で「向かいの軒下に十一、二歳の女の子がいて、ボロボロの服にうずくまっていた。」「そっと母の財布から50銭紙幣を盗み・・汚れた手のひらに丸めた紙幣をのせた。」「・・近くのお寺の陽だまりの隅にボロボロの服にくるまり冷たくなった女の子がいた。・・手の中に50銭札があったという。」「母は5年前、99歳で逝った。とうとう母にも話せなかった。『母さん』とつぶやいた女の子の泣き声が心の隅に今も張りついている。」
京都の福知山市で長らく議員をしていた99歳の平野力さんという方が、よくこの欄に投書をしている。私は彼が90代前半くらいの頃から紙面で名前を見つけ、よく投書を読んでいた。投書の内容は日々の生活だったり、昔の思い出だったり。特にご自身の祖母が駅のことを「ステンショ」と呼んでいたエピソード(2017年11月5日号)、父親が旧制一高や三高の寮歌を歌っていたこと(2020年7月19日号)が印象深い。90代の人物が語る江戸時代生まれの祖母と、抑留から帰国する3か月前に亡くなった父はこの他にもたびたび投書に出てくる。
平野さんについてはシベリア抑留体験時の記事があるのでリンクを掲載する。
「京都)極寒の抑留生活、語り続ける 福知山の平野さん」
「スターリン時代と変わらない」 77年前のシベリア連行とウクライナ重ねる元抑留者
上記のほか取材記事としては「しんぶん赤旗(日刊)」2021年8月29日号等にも登場している。
「あばれたのはあの一度きり」2022年11月5日赤旗
東京都の70代女性の投書は、1年前に亡くなった愛犬「ベルモ」のお話し。「わが家には『ベルモ』という名の大きめの犬がいました。」穏やかで優しいエピソードをつづり「家の中の自分の場所でゆったりと過ごしていました。」
「暴れたのは一度。夫が亡くなって帰ってきた時だけ。お医者さんに安定剤を注射してもらい落ち着きました。」
ちなみに投書の表題を設定するのは、ほぼ編集部である。私の投書が掲載されたときはそうだった。編集部はこの投稿の「転」であるエピソードを表題にしたのだ。上質な散文詩を思わせるこの投稿に適切な表題を付けている。
新聞投稿する人は、投稿欄を見ればよくわかるが、高齢者が多い。なので意識的に新聞は若い人の投稿を掲載する傾向がある。
ここ10年位からは、読者投稿に目を向けることが多くなった。いわゆる「投稿欄」には多くの無名な人々の投稿が掲載され、時にさりげなく有名人が投稿もしていたりする。SNS時代になってからは、時々投稿が引用され拡散されるようにもなった。
もう5年前になる。
毎年同じ日に投稿していた早乙女勝元氏
「妻が願った最後の『七日間』」2018年3月9日朝日新聞
朝日新聞に掲載された「1月中旬、妻容子が他界しました。入院ベッドの枕元のノートに『七日間』と題した詩を残して。」から始まる、この非常に切ない内容の投稿はあっという間に大バズリし、書籍にもなったと聞く。この投稿は3月9日朝刊だったが、そのすぐ下の欄には、早乙女勝元氏の投稿「3月10日に消えた声を語り継ぐ」が載っている。つい最近鬼籍に入られた早乙女さんは、ライフワークとなった東京大空襲を語り継ぐために、毎年3月10日付近に朝日新聞に投書を寄せるのだ。そしてそれを同紙は毎年掲載し続けた。
有名人の意外なエピソードが、当時を知る人々によって語られることもある。
「『お色気』大切 加古さんの一言」2019年3月24日赤旗日曜版
この日のしんぶん赤旗日曜版の読者コーナー「人生のうた」には1959年に創刊された日曜版と絵本作家のかこさとし氏のエピソードが載っている。
創刊号に掲載されたブリジット・バルドーをみた当時30代だったかこさとし氏が「共産党さんも考えましたね。お色気というのは大切ですよ。私たちもみんなバルドーさんのこと知ってるじゃないか」と話して大笑いになったことが紹介されている。
「人生のうた」は比較的高齢の投稿者が多く、考えさせられる内容も多い。
「50銭札盗んで女の子に渡す」2017年10月29日赤旗日曜版
戦後避難先で「向かいの軒下に十一、二歳の女の子がいて、ボロボロの服にうずくまっていた。」「そっと母の財布から50銭紙幣を盗み・・汚れた手のひらに丸めた紙幣をのせた。」「・・近くのお寺の陽だまりの隅にボロボロの服にくるまり冷たくなった女の子がいた。・・手の中に50銭札があったという。」「母は5年前、99歳で逝った。とうとう母にも話せなかった。『母さん』とつぶやいた女の子の泣き声が心の隅に今も張りついている。」
京都の福知山市で長らく議員をしていた99歳の平野力さんという方が、よくこの欄に投書をしている。私は彼が90代前半くらいの頃から紙面で名前を見つけ、よく投書を読んでいた。投書の内容は日々の生活だったり、昔の思い出だったり。特にご自身の祖母が駅のことを「ステンショ」と呼んでいたエピソード(2017年11月5日号)、父親が旧制一高や三高の寮歌を歌っていたこと(2020年7月19日号)が印象深い。90代の人物が語る江戸時代生まれの祖母と、抑留から帰国する3か月前に亡くなった父はこの他にもたびたび投書に出てくる。
平野さんについてはシベリア抑留体験時の記事があるのでリンクを掲載する。
「京都)極寒の抑留生活、語り続ける 福知山の平野さん」
「スターリン時代と変わらない」 77年前のシベリア連行とウクライナ重ねる元抑留者
上記のほか取材記事としては「しんぶん赤旗(日刊)」2021年8月29日号等にも登場している。
「あばれたのはあの一度きり」2022年11月5日赤旗
東京都の70代女性の投書は、1年前に亡くなった愛犬「ベルモ」のお話し。「わが家には『ベルモ』という名の大きめの犬がいました。」穏やかで優しいエピソードをつづり「家の中の自分の場所でゆったりと過ごしていました。」
「暴れたのは一度。夫が亡くなって帰ってきた時だけ。お医者さんに安定剤を注射してもらい落ち着きました。」
ちなみに投書の表題を設定するのは、ほぼ編集部である。私の投書が掲載されたときはそうだった。編集部はこの投稿の「転」であるエピソードを表題にしたのだ。上質な散文詩を思わせるこの投稿に適切な表題を付けている。
新聞投稿する人は、投稿欄を見ればよくわかるが、高齢者が多い。なので意識的に新聞は若い人の投稿を掲載する傾向がある。
電子版の新聞のこと ~Wall Street Journalを購読する [ガジェット]
新聞が電子化されてきた。日本ではだいたい紙の新聞より若干安く設定され、かつデジタル版限定のコンテンツにもアクセスできるというのが売りのようだ。
しかし私は電子版の新聞を購読していない。無料版は読むが。
けれど最近電子版の新聞を購読し始めた。その新聞は「Wall Street Journal(WSJ)」。
The Wall Street Journal日本版
*現状では英語と日本語、中国語が選択可能。Web版ではタイトルの直下のメニューで言語を選択する。

アプリ(日本語)画面
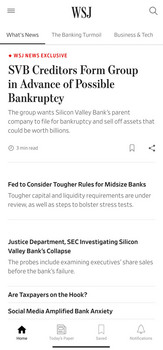
アプリ(英語)画面

Web版(日本語)画面
コンテンツについて 英語はDeepLでほぼ解決
米国の新聞なので基本は英語なのである。が、WSJは日本語版が用意されている。これが他の英字新聞にはない特徴。しかし日本語版は本国版から翻訳をする関係で、どうしても記事が遅く少なく、最新ニュースは当然ながら英語版が早い。
英語を読むの最近しんどいのだが、実は新聞の英語はDeepL翻訳との相性が非常に良い。文章の構成が単純でミススペルもほぼないから。
まあ時々センテンス丸々一つ無視して翻訳されるのが玉にキズだが。
アプリで記事のテキストを選択して、Androidならそのままワンクリックで翻訳される。超便利。
プリント版(紙版)は実はとても大事
WSJはアプリに「Print Edition」がある。紙の新聞は、一面に掲載される記事はその新聞社が一番重要と判断した内容になる。これはある程度の年齢の人には常識なのだが、電子版で読んでいると何が重要で何が軽いニュースなのかわかりにくい。プリント版があると、その日の一面は何かわかるので参考になる。
しかもこのアプリ、プリント版を画面表示させて記事をクリックすると、電子版のように表示される。当然翻訳もワンクリックだ。超便利。

プリント版の画面

特定の記事をクリックするとこのような記事表示画面に遷移する
WSJの購読を解約したいときは
WSJの解約はちょっと面倒だ。専用窓口に電話しなければならない(らしい)。
該当情報も探しにくいので、リンク先もあわせて提示する。
「連絡先 顧客サービス」のページ
対応言語: 日本語/英語
フリーダイヤル: 0120-779-868
Eメール: service@wsj-asia.com
営業時間: 月曜日~金曜日 09:00~17:30(日本時間)※年始年末・クリスマス・祝日を除く
グローバルサポート: https://help.wsj.com/global
AndroidやiPhoneのアプリで定期購読した場合は以下の連絡先となるようだ。
アンドロイドのアプリ:Google
フリーダイヤル: 0120‐950‐065
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481
iOSのアプリ:Apple
フリーダイヤル:0120-277-535 / 海外からかける場合:(81) 3-6365-4705
https://support.apple.com/ja-jp/HT202039
*このBlogからではなく常に顧客サービスページを参照の上、お電話をお願いします。
英字新聞の優位性
しかし私は電子版の新聞を購読していない。無料版は読むが。
けれど最近電子版の新聞を購読し始めた。その新聞は「Wall Street Journal(WSJ)」。
The Wall Street Journal日本版
*現状では英語と日本語、中国語が選択可能。Web版ではタイトルの直下のメニューで言語を選択する。

アプリ(日本語)画面
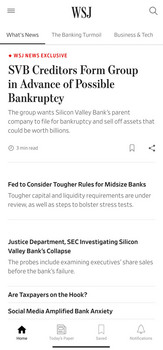
アプリ(英語)画面

Web版(日本語)画面
コンテンツについて 英語はDeepLでほぼ解決
米国の新聞なので基本は英語なのである。が、WSJは日本語版が用意されている。これが他の英字新聞にはない特徴。しかし日本語版は本国版から翻訳をする関係で、どうしても記事が遅く少なく、最新ニュースは当然ながら英語版が早い。
英語を読むの最近しんどいのだが、実は新聞の英語はDeepL翻訳との相性が非常に良い。文章の構成が単純でミススペルもほぼないから。
まあ時々センテンス丸々一つ無視して翻訳されるのが玉にキズだが。
アプリで記事のテキストを選択して、Androidならそのままワンクリックで翻訳される。超便利。
プリント版(紙版)は実はとても大事
WSJはアプリに「Print Edition」がある。紙の新聞は、一面に掲載される記事はその新聞社が一番重要と判断した内容になる。これはある程度の年齢の人には常識なのだが、電子版で読んでいると何が重要で何が軽いニュースなのかわかりにくい。プリント版があると、その日の一面は何かわかるので参考になる。
しかもこのアプリ、プリント版を画面表示させて記事をクリックすると、電子版のように表示される。当然翻訳もワンクリックだ。超便利。

プリント版の画面

特定の記事をクリックするとこのような記事表示画面に遷移する
WSJの購読を解約したいときは
WSJの解約はちょっと面倒だ。専用窓口に電話しなければならない(らしい)。
該当情報も探しにくいので、リンク先もあわせて提示する。
「連絡先 顧客サービス」のページ
対応言語: 日本語/英語
フリーダイヤル: 0120-779-868
Eメール: service@wsj-asia.com
営業時間: 月曜日~金曜日 09:00~17:30(日本時間)※年始年末・クリスマス・祝日を除く
グローバルサポート: https://help.wsj.com/global
AndroidやiPhoneのアプリで定期購読した場合は以下の連絡先となるようだ。
アンドロイドのアプリ:Google
フリーダイヤル: 0120‐950‐065
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481
iOSのアプリ:Apple
フリーダイヤル:0120-277-535 / 海外からかける場合:(81) 3-6365-4705
https://support.apple.com/ja-jp/HT202039
*このBlogからではなく常に顧客サービスページを参照の上、お電話をお願いします。
英字新聞の優位性
「超左翼おじさん」の除名の件 ~日本共産党は明らかにやりすぎ [社会情勢]
なんだかずいぶん昔に見たことがあるような...。90年代の半ばくらいまではこんなものを目にしたが...。
という印象を持ったのは、最近の「しんぶん赤旗」に良く載る「何かを批判する論文」だ。
規約と綱領からの逸脱は明らか――松竹伸幸氏の一連の言動について
党攻撃とかく乱の宣言――松竹伸幸氏の言動について
「結社の自由」に対する乱暴な攻撃――「朝日」社説に答える
事実踏まえぬ党攻撃 「毎日」社説の空虚さ
怖い怖い。文体が怖い。セレクトする単語が怖いぞ。
これ今年2023年の1月に刊行された「シン・日本共産党宣言」という-悪いんだけどちょっと書名のセンスがなあ-という新書の著者にまつわる様々な出来事がその発端になっている。
「出来事」と書いたが著者の問題ではない。著者の行動に対して共産党がとった反応が物議をかもしているのである。


シン・日本共産党宣言 ヒラ党員が党首公選を求め立候補する理由 (文春新書) Kindle版
経過としては以下の通りである
・松竹伸幸氏がBlog「超左翼おじさんの挑戦」で持論を展開する。AbemaPRIMEなどにも出演
・2023年1月19日。松竹氏、安全保障や党首公選制を求める意見等が記された「シン・日本共産党宣言」を発刊
・同日松竹氏日本記者クラブで記者会見
・21日しんぶん赤旗にて批判記事(上記リンク参照)
・2月5日、共産党地区委員会が松竹氏除名を決定
・2月6日共産党京都府委員会で松竹氏の除名を承認。組織上除名確定
・同日松竹氏日本記者クラブで記者会見
・7日新聞各紙で報道。その後も社説やコラム等で各紙が除名を批判
・赤旗に連日松竹氏とマスコミの批判記事が掲載される(上記リンク参照)
まあ、こんな感じなんですが。
安全保障論について、私は自衛隊に対して、それは軍隊であると考えているし、そもそも暴力装置に対しては活用し、利用する存在と考えている。だから彼が言うように「・・護憲派がこぞって「自衛官を愛し、活かしたい」という考えの上で「だから九条を守る」と言えるなら、その時初めて「九条派」と「自衛隊派」の間に議論が成立するのではないか、と考えたのです。」(サイトSAKISIRU2021年12月記事)とも考えていない。
*サキシルは代表がHanadaに連載持っているような人なのでリンクは貼らない。しかもこの記事、リードに「元共産党の「超左翼おじさん」」って書いてるけど、この時点では共産党員でしょうに。そういうとこだぞ、サキシル!
「自衛隊」なるものはさ、旧軍の歴史を継続してると公言してるし、歴代幹部がクソ右翼かそれに近いし、講演会に竹田恒泰みたいな皇族を僭称するビジネス右翼を講演会に招くようなクソ組織なんだよね。そこは松竹氏、考えてほしいよね。
松竹氏は自身で意見を発信するだけではなく、わりかし無節操にこうしたサイトにも登場するものだから、一部の左翼からは共産党を右に引っ張る人物だ、として批判されていた。私の知るところでは、ね。
著書を読んでみる
まあ何も読まずして共産党中央の意見を垂れ流すのも、よく知らずに中央を批判するのもどうかと思う。赤旗の記事は読んだ。それで「シン・日本共産党宣言」を買って読んでみる。
ざっくりした感想を言うと、この本は特に共産党がこれまで野党共闘路線で進めてきた諸政策-特に安全保障政策-を、あいまいなままにせず段階論を設定して、その段階にあった政策を明示せよということだ。現段階では自衛隊容認・日米安保維持。実はこれは共産党も前から野党共闘で言い続けている。松竹氏は安保維持だけではなく、核抑止力を除いた専守防衛を提案している。専守防衛については2015年の「戦争法」以前の政策に合致する。
とまあこんな感じで、共産党のこの間の政策と綱領と規約に沿ったかたちでの提案を行っていると私は読んだ。さすがは長い党歴を持つ共産党員ならではの著作である。
「党首公選制」もこれまで共産党内で政策として否定しているわけではなく、それを取り上げて発表することは規約違反でもない、としている。これもよくわかる。
*まあでもね。「党首」って言葉を社会党が使い始めたのが90年代半ばで、その時は委員長じゃないのか自民党に合わせたのかと批判があったんだよ結構ね。
なぜ彼が除名になったのか
という印象を持ったのは、最近の「しんぶん赤旗」に良く載る「何かを批判する論文」だ。
規約と綱領からの逸脱は明らか――松竹伸幸氏の一連の言動について
党攻撃とかく乱の宣言――松竹伸幸氏の言動について
「結社の自由」に対する乱暴な攻撃――「朝日」社説に答える
事実踏まえぬ党攻撃 「毎日」社説の空虚さ
怖い怖い。文体が怖い。セレクトする単語が怖いぞ。
これ今年2023年の1月に刊行された「シン・日本共産党宣言」という-悪いんだけどちょっと書名のセンスがなあ-という新書の著者にまつわる様々な出来事がその発端になっている。
「出来事」と書いたが著者の問題ではない。著者の行動に対して共産党がとった反応が物議をかもしているのである。

シン・日本共産党宣言 ヒラ党員が党首公選を求め立候補する理由 (文春新書) Kindle版
経過としては以下の通りである
・松竹伸幸氏がBlog「超左翼おじさんの挑戦」で持論を展開する。AbemaPRIMEなどにも出演
・2023年1月19日。松竹氏、安全保障や党首公選制を求める意見等が記された「シン・日本共産党宣言」を発刊
・同日松竹氏日本記者クラブで記者会見
・21日しんぶん赤旗にて批判記事(上記リンク参照)
・2月5日、共産党地区委員会が松竹氏除名を決定
・2月6日共産党京都府委員会で松竹氏の除名を承認。組織上除名確定
・同日松竹氏日本記者クラブで記者会見
・7日新聞各紙で報道。その後も社説やコラム等で各紙が除名を批判
・赤旗に連日松竹氏とマスコミの批判記事が掲載される(上記リンク参照)
まあ、こんな感じなんですが。
安全保障論について、私は自衛隊に対して、それは軍隊であると考えているし、そもそも暴力装置に対しては活用し、利用する存在と考えている。だから彼が言うように「・・護憲派がこぞって「自衛官を愛し、活かしたい」という考えの上で「だから九条を守る」と言えるなら、その時初めて「九条派」と「自衛隊派」の間に議論が成立するのではないか、と考えたのです。」(サイトSAKISIRU2021年12月記事)とも考えていない。
*サキシルは代表がHanadaに連載持っているような人なのでリンクは貼らない。しかもこの記事、リードに「元共産党の「超左翼おじさん」」って書いてるけど、この時点では共産党員でしょうに。そういうとこだぞ、サキシル!
「自衛隊」なるものはさ、旧軍の歴史を継続してると公言してるし、歴代幹部がクソ右翼かそれに近いし、講演会に竹田恒泰みたいな皇族を僭称するビジネス右翼を講演会に招くようなクソ組織なんだよね。そこは松竹氏、考えてほしいよね。
松竹氏は自身で意見を発信するだけではなく、わりかし無節操にこうしたサイトにも登場するものだから、一部の左翼からは共産党を右に引っ張る人物だ、として批判されていた。私の知るところでは、ね。
著書を読んでみる
まあ何も読まずして共産党中央の意見を垂れ流すのも、よく知らずに中央を批判するのもどうかと思う。赤旗の記事は読んだ。それで「シン・日本共産党宣言」を買って読んでみる。
ざっくりした感想を言うと、この本は特に共産党がこれまで野党共闘路線で進めてきた諸政策-特に安全保障政策-を、あいまいなままにせず段階論を設定して、その段階にあった政策を明示せよということだ。現段階では自衛隊容認・日米安保維持。実はこれは共産党も前から野党共闘で言い続けている。松竹氏は安保維持だけではなく、核抑止力を除いた専守防衛を提案している。専守防衛については2015年の「戦争法」以前の政策に合致する。
とまあこんな感じで、共産党のこの間の政策と綱領と規約に沿ったかたちでの提案を行っていると私は読んだ。さすがは長い党歴を持つ共産党員ならではの著作である。
「党首公選制」もこれまで共産党内で政策として否定しているわけではなく、それを取り上げて発表することは規約違反でもない、としている。これもよくわかる。
*まあでもね。「党首」って言葉を社会党が使い始めたのが90年代半ばで、その時は委員長じゃないのか自民党に合わせたのかと批判があったんだよ結構ね。
なぜ彼が除名になったのか
前の10件 | -

